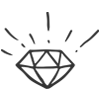読み終えたあと「これを書いてくれてありがとう」と頭を垂れる類の本があって、『この地獄を生きるのだ』はそういう本です。『傷口から人生。』や『さびしすぎてレズ風俗に行きましたレポ』に近い後読感。
著者は就職浪人ののち、エロ漫画雑誌の出版社に就職したものの、そこは月給12万、ボーナスなし、残業代なし、社会保険なしのブラックな職場。多忙と貧困により心を病み、自殺未遂を起こして精神病院に入院、退院後はデイケアに通いながら生活保護を受けるも、待っていたのはケースワーカーとの不和、患者を食い物にする貧困ビジネス、圧倒的な自尊心の欠落。そして再びの自殺未遂…。
文字を打っているだけで息が詰まってくる。そんな「地獄」から、著者がいかに脱出し、再生したかが書かれているエッセイです。著者が今は回復の途中にあり、自立就労に成功していると知っていても、ほとんど祈るような気持ちで読みました。しんどい。
しんどいんですけど、どんどん読んでしまう。淡々とした語り口の文章もうまいし、何より読めば読むほど「他人事ではない」と思えてくる。
健常者と障害者の境目はあるようでない。あるのは立場の違いだけである。
小林エリコ『この地獄を生きるのだ」位置.1201
私が「他人事ではない」と感じる理由のひとつに、大学時代の経験がありまして。おそらく軽度のうつ状態だったんですよね。おそらく、というのは当時通院して病名をもらったわけではなく、自分の状態が何であるかよくわからないままだったからなのですが、後になって考えてみればそうだったんじゃないかと。
うつは突然やってきました。バイトの同僚数人とカフェにいたとき、急にみぞおちのあたりに不安のような焦燥感のような、それらが混ざりあったような、味わったことのない感覚が起こり、彼女たちの話がうまく頭に入らなくなったのです。聞こえているのに頭に入らない。なんだこれは。
状況が理解できないまま、みぞおちの感覚は次第に重くなり、同時に感情が途切れ途切れになっていくのを感じました。みんなが笑っているけど何が楽しいのかわからない。怒っていても、悲しんでいてもわからない。
そのあたりで、私の様子がおかしいのに気づいた隣の子が「体調が悪いのではないか」「大丈夫か」と聞いてくれました。体調が悪いのとは少し違ったのだけれど、なんと言えばいいのかわからないし、実際に顔色は悪くなっていたのだと思う。
私はお礼と謝罪を述べて先に帰らせてもらいましたが、駅まで歩いていくその間にも、感情がどんどん断線していく。家にたどり着いたときには、ほとんど何も受信できなくなっていて、何が悲しいのか全くわからないままわんわんと泣き続けました。びっくりした家族に「何かあったのか」と聞かれたけれども、それもうまく説明できない。
どれくらい泣いたのか、涙も出なくなったころ、ぎゅうぎゅうに膨らんでいた不安や焦燥感のようなものは消え去り、後にはがらんとした空間だけが残されました。比喩ではなく、本当にお腹のあたりがスカスカするように感じられる。空っぽだ、これが絶望なのだろうか、とぼんやり思い、がらんどうの自分を確かめているうちに、ただひとつ、はっきりとわかることがありました。真っ白な部屋に1枚だけ書き残されたメモのようなそれは、「私は私のことが大嫌いである」という事実だったのです。
自分を全く愛せていない状態が、実際には何年も続いていたのですが、無意識にそこから目をそらし、過剰な個性の演出や表面的に尖ったふるまいによって、あたかも肯定できているかのように誤魔化し、自身と向き合うことを避け続けた、その負荷が限界に達したのです。バイトには行けなくなり、そこからしばらく、家と大学の往復だけを何とかこなし、家にいる間は真っ暗の部屋で呆然と座っているか泣いているだけの日々が続きました。
書いておきながらちょっと恥ずかしくもなってくる。若かったとはいえ、著者が対峙する現実の苦さに比べれば、何という甘っちょろさよ。しかし、その時点においては、それが私の直面するすべてであったし、何より自尊心の壊滅的な欠落という深刻な問題がありました。
私はこの状況を「最低」だと感じる。どこにも所属せず、何の役割も持たず、果たすべき役目もない人生。空っぽで虚無だ。
小林エリコ『この地獄を生きるのだ」位置.460
人は自尊心を失うと、幸せに生きるのが難しくなる。著者の場合、失った自尊心を取り戻すには、自分がこの社会の中で必要とされている実感を得ることが不可欠だと考えていて、そのために職を得て社会と繋がり自立すべく、幾度となく折れながらも奮闘を続けます。
普通に働いて、普通に生きたかった。その「普通」が、いかに手に入れるのが困難なものかを知った。宝石も高価な服も要らない。ただ、その日その日をつつましく生きたいと願っていた。そのつつましく生きるという願いは、この世で最も高価な願いだった。
小林エリコ『この地獄を生きるのだ」位置.1377
普通に働いて、普通に暮らすこと。多くの人にとってそれは普通のこと。しかし、誰にでも「普通」を手放さざるを得ないような状況に陥る可能性があり、一度手放してしまうと取り戻すのは容易ではない。本書を読むとそれがよくわかります。
暗闇を歩くための灯りのように、誰かの助けが必要なのだけれど、著者は親との間に軋轢があり、友達とは疎遠になり、ケースワーカーは信用できず、クリニックには利用され、一人で困難に立ち向かわなくてはならなかった。大学時代の私が、地獄の淵に立って底の見えない穴を覗き込みながらも、一旦そこに留まることが許されたのは、家族と暮らしていたからです。
感情的な激しい衝突は何度もあったけれど、追い出されることはなかったし強い共依存関係に陥ることもなかった。おかげで、転げ落ちてきた坂を少しずつ登って元の道に戻る力が生まれるまで、その場に座り込むことができたわけですが、できたこと自体が幸運だったんですよね。
どの道もどこかで地獄につながっている。私や著者は「運よく」そこから戻ってくることができた。もちろん、著者の場合は単に運ではなくて、就労したいという強い気持ちを持ち続け、努力を続けられたからこそですが、もし編集者としての経験がなかったら、クリニックの待合室で雑誌を読まなかったら、どうなっていたはわからない。
人は必ず年老いて、いつか弱者になる。働くことのできない人々が生活保護や福祉サービスを受けることを責めるような世の中は、想像力の貧しい社会なのだ。
小林エリコ『この地獄を生きるのだ」No.1337
生きづらさを抱え、社会にうまく順応できないと感じている人には何かしら響くものがあるだろうし、そうでない人はそれゆえに想像しにくいであろう「社会というシステムの中で躓いてしまった人」の実態を、生々しい手触りをもって知ることができます。どんな問題の解決も、知ってもらうところからがスタート。多くの人に手にとってほしい一冊です。
この地獄を生きるのだ うつ病、生活保護。死ねなかった私が「再生」するまで。
小林エリコ/イースト・プレス
後半、ひとつひとつ取り戻される普通の日常がきらきらして泣ける。
こちらもおすすめ
傷口から人生。 メンヘラが就活して失敗したら生きるのが面白くなった
小野美由紀/幻冬舎
人生のうまくいかなさを、他人のせいにしたことのあるすべての人に。
さびしすぎてレズ風俗に行きましたレポ
永田カビ/イースト・プレス
複雑で個人的な状況を客観的に把握して説明する力がすごい。